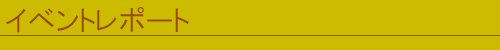「高峰山案内ライド」
恒例の高峰山。いつ行ってもブチ楽しいDHコースです。
12月とは思えない暖かさの中で楽しんだライドの模様を松山さんがレポートしてくれました。
※写真をクリックすると拡大します。
5月に痛めた膝のリハビリのため5年ほど離れていたMTBに再び乗りたくなり、マンションの廊下に眠っていたバイクをお店でメンテナンスして頂いたのが10月頃。その際に走行イベントがあることを教えていただき、今回「高峰山案内ツアー」に参加させてもらいました。バイクは旧式のDHバイクです。
高峰山までは地図をみてもわかりにくい場所ということで、麓のコンビニで集合しそこで参加者同士の自己紹介。グループ分けを行ったあと、皆さんで連れ立って高峰山の駐車場に向かいました。
本当にわかりにくく、最初自力で行くのはかなり難しいと思いました。
 今回コースを案内して下さる方は相坂さんと助っ人の宮さん、それぞれ7名と6名の2グループに分かれてコースを走ります。
今回コースを案内して下さる方は相坂さんと助っ人の宮さん、それぞれ7名と6名の2グループに分かれてコースを走ります。駐車場で準備を済ませ、各自バイクをトランポに積み込みスタート地点を目指すのですが、これがまた激坂でスリル満点!かなりの斜度の未舗装路を高峰山のボスの須藤さんは絶妙のアクセルワークで登っていきます。
15分〜20分ほど揺られてスタート地点に到着し、軽く準備運動をしたあといよいよスタートです。
スタート地点からすぐ麓が見下ろせる視界が開けたところに出るのですが、空も晴れ渡りすばらしい景色です。その日は風もなくポカポカ陽気の絶好のコンディション。最高です。
 1本目は七曲がりコース。
1本目は七曲がりコース。3キロ程の適度に激しいシングルトラックが続くウォームアップにピッタリのコース。
ところどころにバンクがあり、ふかふかの落ち葉の上で軽くドリフトさせたりと、皆さん本当に楽しそうです。
体が温まったところで2本目はバンブーコースという激しめのコースへ。途中道を間違えるというハプニングがありつつも、コース名の由来となっている竹林へ。
一箇所激坂があり、自分は迷わずバイクを降りて押して下りることに(それでも怖かったあ)。
一番最後に相坂さんが下り方を実演してくれていたようなのですが、残念ながら先に下った自分のところからはその雄姿をみることができませんでした。しかし、あの叫び声と皆さんのどよめきからすると本当に雄姿だったのかどうかは・・・・・・。
激坂を抜けた後はダブルトラックのジープロードです。それまでは後ろのほうから皆さんについて行っていたのですが、ここは高速コースなのでフルサスが有利ということで相坂さんのすぐ後ろを走らせて頂きました。
やはり相坂さんの走りは違います。自由自在にバイクを操りながらえらいスピードで下って行きます。後ろについていっていたら曲がりきれず危うく畑に落ちそうになりました。しかし、いやー気持ちよかった。
 午前中2本走ったところでお昼ごはん。
午前中2本走ったところでお昼ごはん。ここには売店がないので事前に調達しておくことが必要です。初めて行かれる方はご注意を。
お昼を食べ終わったところで相坂さんのプチ講習会。マニュアルをレクチャーして下さっていました。
見ていると(自分は見てるだけ・・・・・)、やはりちびっ子は上達が早いですねえ。
そして午後からは2グループ共同で午前中とは別の約6キロの長いコースです。
スタート地点から午前中の2本とは反対方向の階段を登りはじめ・・・・・・、あれ、階段?登り終わったところで下るのも階段、そう、登山道のようです。
階段の脇の細い道や階段そのものを下っていくのですが、途中に木が生えていたりして結構怖かったです。
途中、登山道を左にそれるとまたまた楽しいシングルトラックのコースのはじまりです。しばらく落ち葉でふかふかのシングルトラックを楽しみながら下って行くと、最後にぱっと視界が開けフリーライドパークが現れます。
 今はあまりメンテナンスがされていなくて下が柔らかい状態とのことでしたが、バームや小さなテーブルトップがあり楽しそうなコースレイアウトです。
今はあまりメンテナンスがされていなくて下が柔らかい状態とのことでしたが、バームや小さなテーブルトップがあり楽しそうなコースレイアウトです。そしてパークの真ん中に蟻地獄のような360度バンクになったお椀型のアイテムがあり、その真ん中には水溜りが。バンクを走りきってお椀から抜け出すのはかなり難しそうです。
そこで相坂さんが先陣をきってトライしてくれました。皆さんの声援を背に受けバンクを300度ほど周り、おおっ!さすがっ!と思ったその瞬間、肩から撃沈!!いやー、盛り上げていただきました。お椀アイテム恐るべし。
その後はテーブルトップでジャンプ合戦。皆さんきれいに抜けて気持ちよさそうでした。
さんざん遊んだところで駐車場まで自走して戻りお開きとなりました。
 いやー楽しかった。天気もいいし、景色もいいし、特にふかふかの落ち葉の上、木漏れ日の下を走るのは最高に気持ちよかったです。
いやー楽しかった。天気もいいし、景色もいいし、特にふかふかの落ち葉の上、木漏れ日の下を走るのは最高に気持ちよかったです。"やっぱ、楽しいわ、ちゃり"、と実感した大満足の一日でした。
高峰山、いいところです。いろんなレベルの人が楽しむことができると思います。皆さんも是非!おすすめ!!
そしてスタッフの皆さん、参加者の皆さん、お世話になりました。
どうもありがとうございました。
== SPECIAL THANKS ==
Written by Matsuyama
Written by Matsuyama